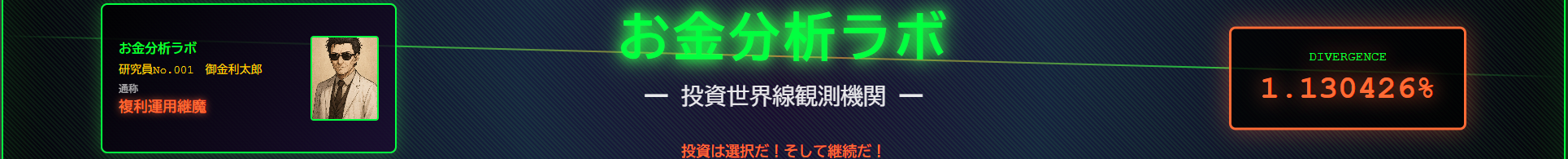配当利回り9%。
自社株買い1000億円。
ふつうなら「即買い」だ。
だが私は、一株も買わなかった。
2025年9月29日、ソニーフィナンシャルグループ(以下、ソニーFG)が東証プライム市場に再上場しました。配当利回り9%、1000億円の自社株買いという派手な株主還元策が話題になっています。
一見すると非常に魅力的な高配当株に見えます。
しかし、私はこの銘柄に強い違和感を覚えました。
なぜか?
それは、わずか5年前に約4000億円かけて完全子会社化した事業を、今になって切り離すという異常な行動だからです。
この裏に何が隠れているのか。時系列とデータから読み解いていきます。
パーシャルスピンオフとは?
まず、今回の上場が通常のIPOとは全く異なることを理解する必要があります。
通常のIPOとの決定的な違い
通常のIPO(新規上場)
- 新株を発行して資金調達
- 会社にお金が入る
- 成長投資のための資金確保が目的
ソニーFGの場合
- 新株発行なし(ダイレクトリスティング)
- 会社は1円も調達していない
- 親会社ソニーグループが保有株式の80%超を株主に現物配当
株主目線で見ると
あなたがソニーグループ株を100株持っていたとします。
スピンオフ前
- ソニーグループ株:100株
スピンオフ後
- ソニーグループ株:100株
- ソニーFG株:●●株(突然もらえる)
価値の総和は理論上変わりません。ソニーグループの中にあった金融事業が独立し、株主に分配されただけです。
その後、もらったソニーFG株をどうするかは株主の自由です。
上場直後の異常な動き
ここで疑問が生まれます。
「上場したのに、なぜ1000億円も使って自社株買い?」
大量の売り圧力
現物配当でソニーFG株を受け取った株主の多くは:
- 「金融株に興味がない」
- 「突然もらっても困る」
- 「とりあえず売ろう」
さらに、インデックスファンドも機械的に売却:
- 上場初日、一時的に日経平均に組み込まれる
- 翌日9月30日に除外決定
- パッシブファンドが約258億円相当を売却
結果
- 上場初値:205円
- その後急落:一時146円
- 基準値段150円を割り込む
自社株買いで株価を支える
この暴落を防ぐため、ソニーFG自身が市場で株を買い戻しています。
自社株買いの規模
- 取得上限:10億株(発行済み株式の約14%)
- 金額上限:1000億円
- 期間:2025年9月〜2026年8月
- 実績(10月中旬時点):約2億株、320億円
つまり株価は、会社自身の買い支えによって維持されている状態です。
ソニーの「金融切り離し」は、逃げなのか戦略なのか?
ここが最も重要なポイントです。
わずか5年前に完全子会社化したばかり
まず、驚くべき事実があります。
2020年5月:ソニーがソニーFHDを約4000億円で完全子会社化(TOB実施)
- 「グループ一体経営」を掲げる
- 「フィンテック強化」を理由に
- 「金融事業の成長を加速」と発表
2020年9月:完全子会社化完了
そして2025年9月:わずか5年でパーシャルスピンオフ
この5年間に何が起きたのか?
2022年:世界的な債券価格の大暴落
2022年、欧米を中心に債券価格が大きく下落し、世界債券の騰落率は▲18.3%と過去30年で最も大きな下落となりました。この下落の主な要因は、欧米で急速に進むインフレを抑制するため、各国の中央銀行が相次いで利上げに踏み切ったことです。
つまり:
- 2020年:低金利・債券価格高騰の時代に完全子会社化
- 2022年:金利急上昇で債券価格が暴落
- 2023-2024年:日銀も金融緩和を終了、金利上昇局面へ
- 2025年:パーシャルスピンオフで切り離し
ソニーグループの思惑(推測)
表向きの理由
- 規制リスクの分離
- 資本効率の改善
- 企業価値評価の明確化
本当の理由(推測)
ソニー生命は、国内金利の一段の上昇リスクを踏まえ、減損処理会計の適用を避けるため保有国債売却を含めて対応する方針を明らかにしています。
つまり:
- 2020年:「金融事業を取り込んで成長」と考えた
- 2022年:債券市場の大暴落で状況が一変
- 2023-2024年:金利上昇リスクが顕在化
- 2025年:リスクが拡大する前に切り離したかった
完全子会社化からわずか5年での方針転換。この異常な短さが、ソニー経営陣の危機感を物語っています。
生命保険業界の構造的リスク
ここが私の最大の懸念点です。
生保ビジネスの特性
生命保険会社は:
- 顧客から預かった保険料を運用
- 超長期の債券で運用(10年、20年、30年、40年物)
- 運用収益で保険金支払いの原資を確保
ソニー生命の実態:数字が語る真実
2025年3月末時点のポートフォリオ
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 総資産(一般勘定) | 11.8兆円 | ソニー生命単体 |
| うち公社債 | 8.6兆円(73%) | 超長期債中心 |
| うち外国債券 | 約20% | |
| うち株式 | 0.07% | ほぼゼロ |
含み損の状況
| 項目 | 含み損 |
|---|---|
| 公社債 | 1兆3667億円 |
| 外国債券 | 8770億円 |
| 合計 | 約2.2兆円 |
出典:ソニー生命 2025年3月期決算資料、Bloomberg報道
この数字は何を意味するのか?
総資産の約19%が含み損。しかも、それを補填できる株式をほとんど持っていない。
2024年4-6月期:損失が現実化
ソニー生命は2024年4〜6月期に:
- 含み損を抱えた債券を売却
- キャピタル損益:513億円の赤字
- 基礎利益を上回る損失
通常、生保は債券売却損を株式売却益で補います。しかし:
- ソニー生命は株式を0.07%しか保有していない
- 補填する手段がない
- 損失がそのまま利益を圧迫
ソニー生命の経営企画部統括部長は「金利上昇は初めての経験」と語っています。
金利上昇が与える影響
債券の基本原理
- 金利が上がる → 債券価格が下がる
- デュレーション(残存年数)が長いほど影響大
- 金利1%上昇 → 30年債は約30%下落
生保への影響
- 2022年の世界的金利上昇で各社苦境に
- 日本でも2024年から本格化
- 今後さらに金利が上昇すれば、含み損は拡大
ソニー生命の危機感
ソニー生命の稲葉亮治執行役員は2025年5月のインタビューで:
- 「超長期債金利の一段上昇リスクには非常に危機感を持っている」
- 減損回避策として「必要に応じて売却などの対応を取る」
つまり、すでに含み損の処理を迫られている状況なのです。
さらに深刻な「解約リスク」
金利上昇がもたらすもう一つの脅威があります。
解約の連鎖
金利が上昇すると:
- 銀行預金の金利が上がる
- 新しい生命保険商品の予定利率が上がる(保険料が下がる)
- 既契約者が「解約して乗り換えよう」と考える
解約が増えると何が起きるか
生保は解約返戻金を支払うため:
- 手元の現金が不足
- 含み損のある債券を売却せざるを得ない
- 損失が確定し、財務が悪化
- さらに解約が増える
この悪循環に陥るリスクがあります。
欧州の保険監督当局の分析によれば、金利上昇局面では:
- 貯蓄性商品の解約率が上昇
- 手元流動性だけではカバーできない
- 含み損債券の売却を強いられる
ソニー生命の場合、2024年4-6月期に「金利上昇で保険契約の中途解約が急増」と報じられています。
つまり、すでに解約リスクが現実化しているのです。
配当利回り9%の真実
ネット上で話題の「配当利回り9%」について検証します。
前提条件を確認する
この数字には、いくつかの楽観的な仮定が含まれています:
1. 年間換算
- 2025年度は半期分のみ(250億円)
- これを年間500億円として計算
2. 自社株買い完了後の株数
- 10億株買い戻した後の約61.5億株で計算
- 現在は約71.5億株
3. 配当性向50%を前提
- 方針は「修正純利益の40-50%」
- 上限で計算している
4. 株価150円前後
- 上場直後の混乱期の価格
現実的な配当利回りは?
保守的に見積もると:
- 実質5-7%程度が妥当
- 2026年度以降は未確定
- 業績悪化なら減配リスクあり
市場が感じている違和感
もし本当に魅力的な銘柄なら、株価はもっと上がるはずです。
株価が上がらない
現状
- 基準値段150円前後で膠着
- 自社株買いがなければ、もっと下がっていた可能性
- PBR 1.86倍は一見高評価だが…
PBRから見る「割高感」
金融セクターとの比較
| 企業 | PBR |
|---|---|
| 三菱UFJ FG | 約0.8倍 |
| 三井住友 FG | 約0.7倍 |
| みずほ FG | 約0.6倍 |
| 生保大手平均 | 約0.4〜0.8倍 |
| ソニーFG | 1.86倍 |
金融セクターの平均からすると、ソニーFGは2倍以上のプレミアム評価です。
これは「ソニーブランド」によるものですが、果たして持続するのか?
異常な自社株買い
1000億円の自社株買いは、ソニーFGの年間純利益に匹敵する規模です。
つまり:
- 1年分の利益を全て自社株買いに使う
- これは通常の企業では考えられない水準
- 株価を支えるために必死という印象
投資家の本音は:
- 「配当利回りは魅力的だが、何かおかしい」
- 「成長性が見えない」
- 「ソニーブランドの恩恵は今後薄れるのでは?」
成長性の欠如
生保市場の現実
- 人口減少で市場は縮小トレンド
- 新規契約獲得は困難
- 競争激化
ソニー生命の強み
- ライフプランナーによるコンサルティング営業
- しかし、これだけで成長できるか?
成長株ではなく、ディフェンシブ高配当株としても中途半端です。
私が買わない4つの理由
1. リスクとリターンが見合わない
- 配当利回り5-7%(実質)
- しかし金利上昇リスク、債券含み損リスクを考えると不十分
- 配当の持続可能性に疑問
2. 「切り離された事業」という事実
- 親会社が手放したかった事業
- 成長性よりも、リスク回避のための分離に見える
- 将来性に疑問符
3. 自社株買いへの依存
- 株価は自社株買いで支えられている
- 2026年8月に終了したら、どうなる?
- 本来の需給では、もっと安い可能性
4. 生保業界の構造的リスク
- 金利上昇リスクが顕在化する可能性
- 債券含み損の拡大
- 運用環境の悪化
配当利回り9%は「お買い得」ではなく「リスクプレミアム」
まとめ
ソニーFGは、表面的には魅力的な高配当株に見えます。
しかし、時系列で見ると全く違う姿が浮かび上がります:
2020年5月:ソニーがソニーFHDを約4000億円で完全子会社化
- 「グループ一体経営」
- 「フィンテック強化」
- 「金融事業の成長を加速」
2022年:世界的な債券価格の大暴落(▲18.3%)
- 各国中央銀行が利上げ
- 長期債券の価格が急落
2024年4-6月期:ソニー生命、損失が表面化
- キャピタル損益513億円の赤字
- 含み損約2.2兆円
- 解約率の上昇
2025年9月:パーシャルスピンオフで切り離し
- わずか5年での方針転換
- 配当利回り9%の高還元
- 1000億円の自社株買い
私が読み取るストーリー
完全子会社化からわずか5年での切り離し。この異常な短さが物語るのは:
- 2020年:低金利時代、金融事業は安定収益源
- 2022年:債券市場の大暴落で状況が一変
- 2023-2024年:金利上昇リスクが顕在化
- 2025年:リスクが拡大する前に切り離す
つまり、高配当と自社株買いは、リスクを覆い隠すための包装紙ではないか?
その裏側には:
- パーシャルスピンオフという特殊な上場
- 2.2兆円の含み損
- 生保業界の構造的リスク
- 金利上昇と解約リスクの連鎖
- 自社株買いに依存した株価形成
- 成長性の欠如
配当利回り9%は「お買い得」ではなく、「リスクプレミアム」です。
私は、より確実な成長性や、明確なビジネスモデルを持つ企業に投資したいと考えています。
投資判断は自己責任で
この記事は個人の見解であり、投資を推奨・非推奨するものではありません。ご自身の判断でお願いします。
あなたはソニーFGをどう見るでしょうか?
「高配当株の新星」か、それとも「ソニーが手放した時限爆弾」か。
私は、静かに距離を取ることを選びました。
配当利回り9%は「お買い得」ではなく、「リスクプレミアム」だ。
高配当の裏に潜むリスクを見抜けるか。それが投資家の力量です。