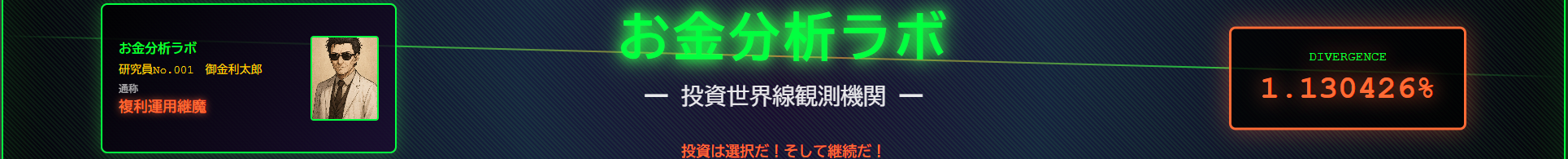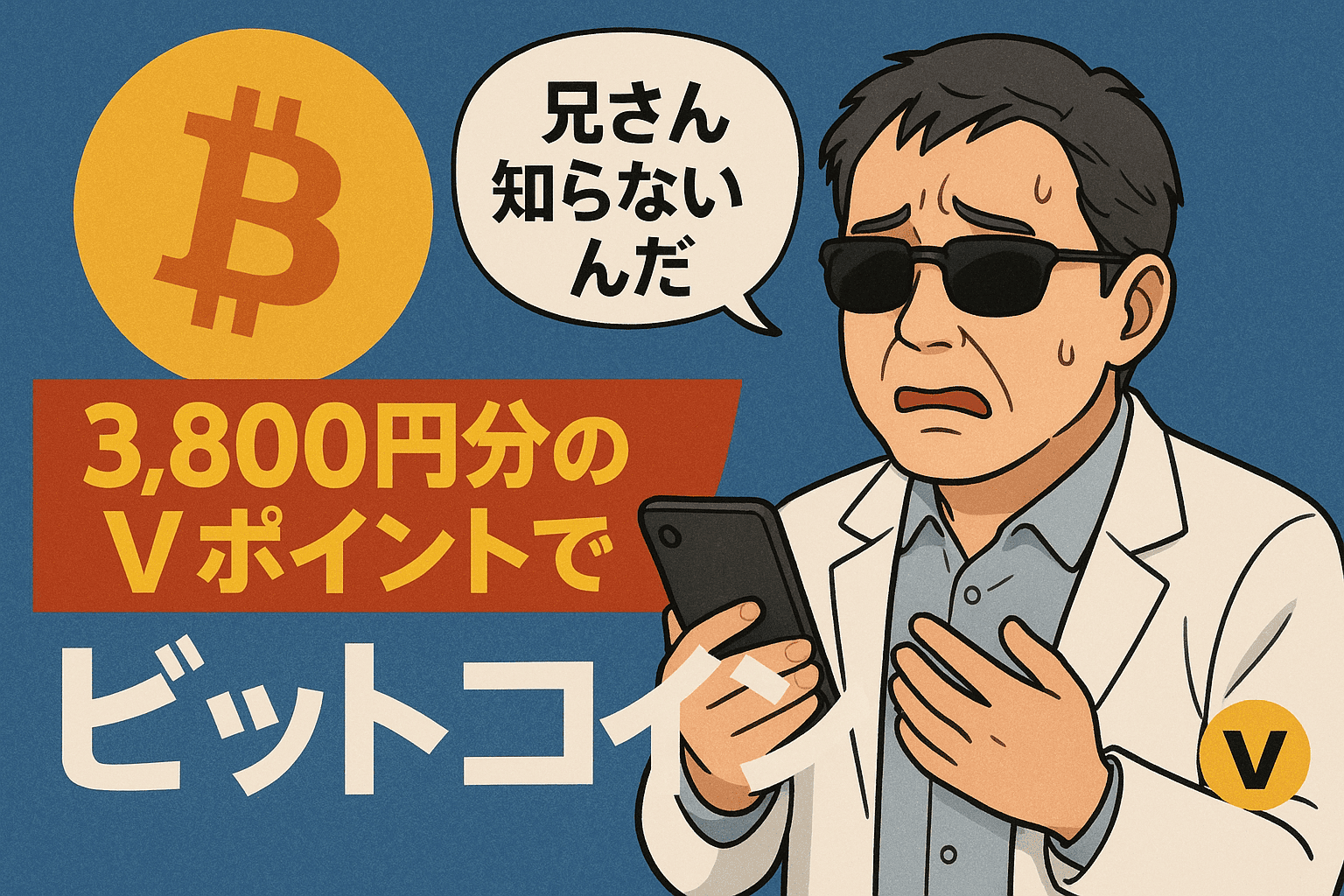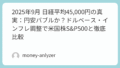2018年、出川哲郎の「兄さん知らないんだ」に背中を押され、私はビットコインに飛び込んだ。結果は——見事なまでの大損。
それでも7年後の今、私はまたビットコインを買っている。今度は現金ではなく、3,800円分のVポイントで。理由はただ一つ、生き残るためだ。
第一章:出川組という烙印
2017年12月、出川哲郎が双子役で演じるコインチェックのCMが始まった。「兄さん知らないんだ」——そのセリフが妙に頭に残って、私はビットコインを買った。200万円を超えていたビットコインを、複数のアルトコインを、「これは来る」と確信して。
もちろん、無くなってもいい金額で。
2018年1月26日。580億円相当のNEMが流出したあの日から、すべてが崩れ始めた。
ビットコインは6分の1に下落した。私が買ったアルトコインの多くは紙くず同然になった。10分の1以下というものもザラだった。「出川組」——そんな呼び方で私たちは語られるようになった。あのCMがきっかけで投資を始めて、そして大損した人たち。
出川哲郎は何も悪くない。彼もまた被害者だった。でも、その名前は私たちの失敗の象徴として刻まれてしまった。
しかし今回は違う。現金ではなく、貯まったVポイントでの再挑戦。失うのはポイントだけという、極めて保守的な戦略での復帰だった。
第二章:冬の時代という試練
2018年から2020年。仮想通貨の冬の時代は想像以上に長く、厳しかった。
毎朝、スマホを見るのが恐怖だった。赤い数字が並ぶポートフォリオ。アルトコインは次々と取引所から上場廃止になっていく。「もう二度と上がらないのではないか」という絶望と、「ここで売ったら本当に終わりだ」という意地の間で、私は揺れ続けた。
こつこつと損切りをしながら、少額ずつ追加投資を続けた。最終的にビットコインとイーサリアムに集約した。あの経験から学んだ教訓——アルトコインには二度と手を出さない。イーサリアムを除いて。
それが正解だったのかどうかは分からない。ただ、生き残ることだけを考えていた。毎日が耐久戦。希望を捨てずに、でも現実も受け入れる。そんな日々が2年以上続いた。
そんな私たちを追い討ちをかけたのが税金の問題だった。
第三章:億り人の税金地獄 – 制度リスクによる大混乱
📊 2017年の億り人:正確には331人
2017年分の確定申告で、仮想通貨取引による収入で1億円以上の雑所得を申告した人は331人いた。これは国税庁が2018年5月25日に初めて公表した数字だ。
しかし、業界関係者は「実際はもっと多いはず」と指摘している。なぜなら、この数字は「正しく申告した人」だけの数字だからだ。
⚖️ 混乱の元凶:段階的なルール明確化と投資家理解のギャップ
当時の投資家の認識
2017年当時、多くの投資家は以下のように考えていた:
❌ 2017年まで広まっていた誤解
- 「暗号資産同士の交換なら、日本円に変えていないから税金はかからない」
- 「現金化していないから、含み益には課税されない」
- 「ビットコイン→アルトコインは物々交換で課税対象外」
これらは、当時のインターネット上で広く信じられていた解釈だった。
国税庁の段階的な方針明確化
実際には、国税庁は段階的に課税ルールを明確化していた:
🗓️ 2014年:国税庁が暗号資産で得た利益は雑所得である旨を示す
🗓️ 2017年9月:FAQで仮想通貨を円に換えた場合の雑所得を明記
🗓️ 2017年12月1日:「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表
この12月の発表で、暗号資産同士の交換時点での時価計算による課税が具体的に示された。
ルールと認識のギャップ
2017年12月にはビットコインが230万円の最高値をつけた。その後、2018年1月には暴落が始まった。
つまり:
- 2017年中:投資家の多くは「交換なら課税されない」と誤解して取引
- 2017年12月:計算方法の詳細が明確化される
- 2018年1月~:暴落で資産激減、しかし2017年分の課税は既に確定
💸 具体的な悲劇のシナリオ
実例:年収300万円の女性投資家
東洋経済新報社の記事で、年収300万円の女性が多額の追徴課税を課せられた事例が報告されている。
典型的な破綻パターン
2017年の行動:
- ビットコイン購入(100万円)
- 値上がり後、アルトコインに交換(時価1000万円)
- 「現金化していないから課税されない」と認識
2018年の現実:
- 900万円の課税対象利益が2017年分として確定
- 最大55%の税率で約500万円の納税義務
- しかしアルトコインは暴落で200万円の価値
- 手元に納税資金なし

🚨 なぜ「制度リスク」と呼ばれるのか
問題の本質
- ルールの認知度が低かった
- 2017年中は暗号資産同士の交換の課税計算方法が十分に周知されていなかった
- 投資家は既存の認識で「現金化していないから課税されない」と判断
- 計算方法の複雑さ
- 2017年12月1日のガイドライン発表で、詳細な計算方法が示される
- しかし、多くの投資家が既に複雑な取引を重ねていた
- 周知と実態のタイムラグ
- 新しい計算方法が2017年分の取引にも適用
- 投資家の理解が追いつかないまま課税が確定
税理士業界の混乱
税理士の間でも「よくわからないし、やりたくない」が6割、「とりあえずやるけど、できることならやりたくない」が3割、「チャンスかも」が1割という状況だった。
専門家ですら混乱していたのが実情だ。
📈 申告できなかった人々の実態
正しく申告できなかった理由
多くの投資家が「正しく確定申告ができなかった・もしくは忘れてしまった」、「税金の支払いが必要となったのに、直後の暴落で利益が消えた」という状況に陥った。
計算の複雑さ
暗号資産同士の交換での課税計算:
- 交換時点の時価で損益計算が必要
- 複数回の交換で計算が極めて複雑
- 「計算できる気がしないので本当に誰かに任せたい」という投資家の声
記録の不備
- 当時は取引所の記録システムも未整備
- 交換レートの正確な記録が困難
- 2018年以降、国税庁が交換業者に「年間取引報告書」の交付を依頼。2017年分は交付されない場合あり
💀 億り人でも破産する現実
税務調査の強化
国税庁の資料によると、2023年の仮想通貨に関する税務調査件数は615件で、前年比約138%の高水準となっている。
税務調査の手法:
- 仮想通貨取引所からの取引データ取得
- ブロックチェーンの取引記録追跡
- 銀行口座との照合
追徴課税の重さ
あるサラリーマンのケースでは、複数回の暗号資産交換により累計5,000万円の申告漏れが発覚し、約1,600万円の追徴税額となった事例が報告されている。
🎓 出川組が学んだ最大の教訓
税制の不透明性リスク
2017年の経験から学んだ最重要な教訓:
💡 「税制や規制が不明確な投資には制度リスクがある」
これは単なる投資リスクではなく、制度リスクだった。ルールが段階的に明確化される過程で、投資家の理解と実際の課税の間にギャップが生じ、多くの混乱を招いた。
第四章:復活、そして新たな恐怖
2021年以降、ビットコインは復活した。私の投資額も10倍以上になった。投資額が小さかったので絶対額は大したことないが、それでも「生き残って良かった」と心底思った。
あの絶望的だった冬の時代を耐え抜いた自分を、初めて褒めてやりたくなった。
しかし、市場は2018年とは別世界に変わっていた。ブラックロックがETFを申請したニュースを見た時、正直信じられなかった。あの保守的なブラックロックが?テスラやマイクロストラテジーが企業資産として保有するニュースも衝撃だった。そして今や、米国で現物ビットコインETFが承認され、機関投資家の参入が現実となった。
2025年の大統領令で401(k)年金制度への組み入れ見直しや戦略的ビットコイン準備方針が示されるなど政策シグナルが出始めた時は、「ついにここまで来たか」と感慨深かった。
でも、新たな恐怖が芽生えていた。税金だ。現在の税制では、今のビットコインを売れば最大55%の税金がかかる。株の20%と比べて異常に重い。そして何より恐ろしいのは相続時のことだった。
第五章:相続時の重税負担という現実
現在の税制では、今のビットコインを売れば最大55%の税金がかかる。株の20%と比べて異常に重い。そして何より複雑なのは相続時の問題だった。
相続時の課税の仕組み(国税庁FAQ準拠)
国税庁FAQに明記されているように、暗号資産を相続した場合:
- 相続税:相続時の時価で評価され、最大55%
- 相続人の取得価額:被相続人が選択していた評価法による死亡時点の評価額(簿価)を引き継ぐ
- 売却時の所得税:引き継いだ簿価との差額に最大55%課税
この仕組みにより、理論上は最大110%の課税が発生する可能性がある。

具体例:14億円のビットコイン相続
被相続人が100万円で購入したビットコインが14億円に値上がりして相続された場合:
- 相続税:約7.7億円(相続時の時価ベース)
- 売却時所得税:約7.6億円(引き継いだ簿価100万円との差額ベース)
- 合計税負担:約15.3億円(資産価値を超える課税)
本当の問題は制度設計の歪み
この問題は、決して他人事ではない。ビットコインを長期保有する全ての人が直面する可能性がある制度設計上の歪みだ。
相続税は相続時の時価で計算されるのに、所得税は被相続人の評価額を引き継ぐ。この二重の評価基準が、理不尽な課税を生み出している。
取得費加算特例の適用外
株式の場合は相続税の一部を取得費に加算できる救済措置があるが、暗号資産は雑所得扱いのため、この特例が適用されない。制度的な救済措置もない状況だ。
第六章:ポイントという希望
だから私が選んだのは、Vポイントでのビットコイン購入だった。
3,800Vポイントで3,230円相当のビットコイン。交換レートで15%程度目減りするが、失うのはポイントだけ。現金は一切使わない。
これは2018年と同じスタンスだ。あの時も私は「無くなってもいい金額」で投資していた。だから損失は小さかったが、利益も小さかった。でも、生き残れた。
そして今回も同じ。失ってもいい「ポイント」だけで、リスクを極限まで抑えながら、それでも「持たざるリスク」に対処する。
なぜか?
現在の税制では、大きく買うのはリスクが高すぎるからだ。でも持たざるリスクも感じている。ビットコインは世界初の分散台帳技術による通貨として、歴史的価値がある。インターネットが続く限り、その価値は残り続けるだろう。
これはオランダのチューリップバブルとは根本的に違う。チューリップは単なる球根だった。でもビットコインは実用的な価値を持つテクノロジーだ。
「インターネットに価値はあるか?」と問われれば、答えは「ある」だ。ビットコインも同じ。法定通貨の裏付けなど必要ない。
第七章:税制改正という光
嬉しいニュースもある。
2024年12月の与党税制改正大綱で、暗号資産を「国民の資産形成に資する金融商品」として位置づけ、20%分離課税への移行が検討事項に明記された。業界団体は2026年度からの実現を要望しており、実現可能性が高まっているが、まだ確定段階ではない。
分離課税導入の効果:
- 税率:最大55% → 約20%へ大幅改善
- 損失繰越控除:3年間の適用
- 年金受給期の社会保険料への影響軽減
ただし、これまでも様々な要望が出されながら実現しなかった経緯もある。金融商品取引法への移行が前提条件とされており、全ての暗号資産が対象になるかは不透明だ。
相続問題は残存
しかし、分離課税が導入されても相続時の根本問題は解決されない:
- 被相続人評価額の引き継ぎは変わらず
- 雑所得扱いのため取得費加算特例は適用外
- 相続税55% + 所得税20% = 最大75%の課税(現行110%から改善だが依然として高負担)
業界団体は相続時の評価方法見直しも要望している。過去3ヶ月平均最安値での評価など、過剰な負担を避ける仕組みを求めているが、こちらは具体的な検討段階には至っていない。
制度改正の優先順位:
- 分離課税導入(20%税率)← 現在の焦点
- 損失繰越控除 ← 同時検討
- 所得区分変更(雑所得→譲渡所得)← 将来課題
- 相続時取得価格リセット ← さらに将来
実現すれば大きな前進だが、完全な解決までは時間がかかる。それまでは現状の重税制度と向き合わなければならない。

第八章:2025年という今
2025年8月現在、ビットコインは史上最高値圏で推移している。2018年の最高値230万円から大幅な上昇を見せている。
「また高値掴みでは?」という不安もある。でも、2018年とは環境が違う。機関投資家が参入し、現物ETFも承認されている。制度的な資産として扱われ始めているのは確かだ。
ただし、米国での政策シグナルは出始めたものの、具体的な制度化は今後のルールメイキング次第だ。それでも、2018年には考えられなかった変化が起きているのは事実だ。
そして私自身の投資スタンスは一貫している。2018年も今も「無くなってもいい金額」での投資。だから損失は小さく、利益も小さい。でも生き残れる。
ポイント投資は、この一貫したリスク管理の延長線上にある。
エピローグ:出川組からの伝言
7年前、私は出川哲郎のCMを見てビットコインを買った。そして大損した。多くの人が市場から去っていった。
でも、私は生き残った。そして今、またビットコインを買っている。今度はポイントで。
ETFだ、機関投資家だ、政策シグナルだと賑わう中、私は3,800円分のポイントで参戦している。笑う人もいるだろう。でも笑われても構わない。2018年から生き残った者の選択は、いつだって慎重だ。
15%の交換レート目減り?ビットコインのボラティリティから見れば誤差の範囲だ。失うのはポイントだけ。得るものは未来への可能性。
税制改正が実現すれば、投資環境は劇的に改善する。相続時の理不尽な課税も部分的に解決されるかもしれない。それまでは、一貫して「無くなってもいい金額」で、リスクを抑えながら長期戦で臨む。
2018年も今も、私の投資スタンスは変わらない。感情ではなく、冷静なリスク管理。大きな利益は望まないが、大きな損失も避ける。この一貫性こそが、出川組が学んだ最大の教訓だ。
2017年の「制度リスク」を経験した投資家たちは今:
- 超少額投資:Vポイントなど「失ってもいい金額」での参戦
- 徹底した記録管理:すべての取引を詳細に記録
- 保守的な税務処理:不明確な部分は最も厳しい解釈で対応
- 税制改正待ち:大きな投資は制度整備を待つ
インターネットが世界を変えたように、ブロックチェーンも世界を変える。ビットコインはその先駆者だ。歴史は繰り返すが、同じではない。2018年の悪夢は、2025年の希望に変わった。
私は出川組だった。そして今は、一貫した希望組だ。
3,800円のポイントに込めた想い。それは過去への継続でもあり、未来への計算された賭けでもある。世界中が注目する中、たった3,800円のポイントで挑む。これが2018年を生き抜いた男の、等身大の勇気だ。
「兄さん、今度は知ってるんだ」
2017年の税制混乱は、単なる「勉強不足」や「甘い考え」が原因ではなかった。制度の周知不足と、投資家の理解が追いつかないスピードでの市場拡大が生んだ混乱だった。
しかし、この経験は貴重な教訓となった。税制や規制の不明確さそのものが最大のリスクであり、それに対する備えこそが、真の意味でのリスク管理なのだ。
出川組が2025年に3,800円のVポイントで再参戦するのは、この痛烈な経験があればこそ。その選択には、7年間の学習コストが込められている。
投資は自己責任で。特に暗号資産は価格変動が激しく、元本割れのリスクがあります。ポイント投資も例外ではありません。過去の経験を踏まえ、失ってもいい金額での投資を強くお勧めします。
※税務に関する記載は2025年8月時点の情報に基づいており、個別の税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。
#ビットコイン #Vポイント #出川組 #暗号資産 #投資体験談 #税制改正