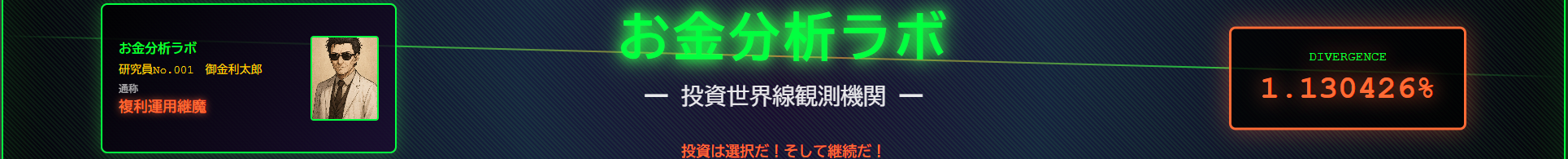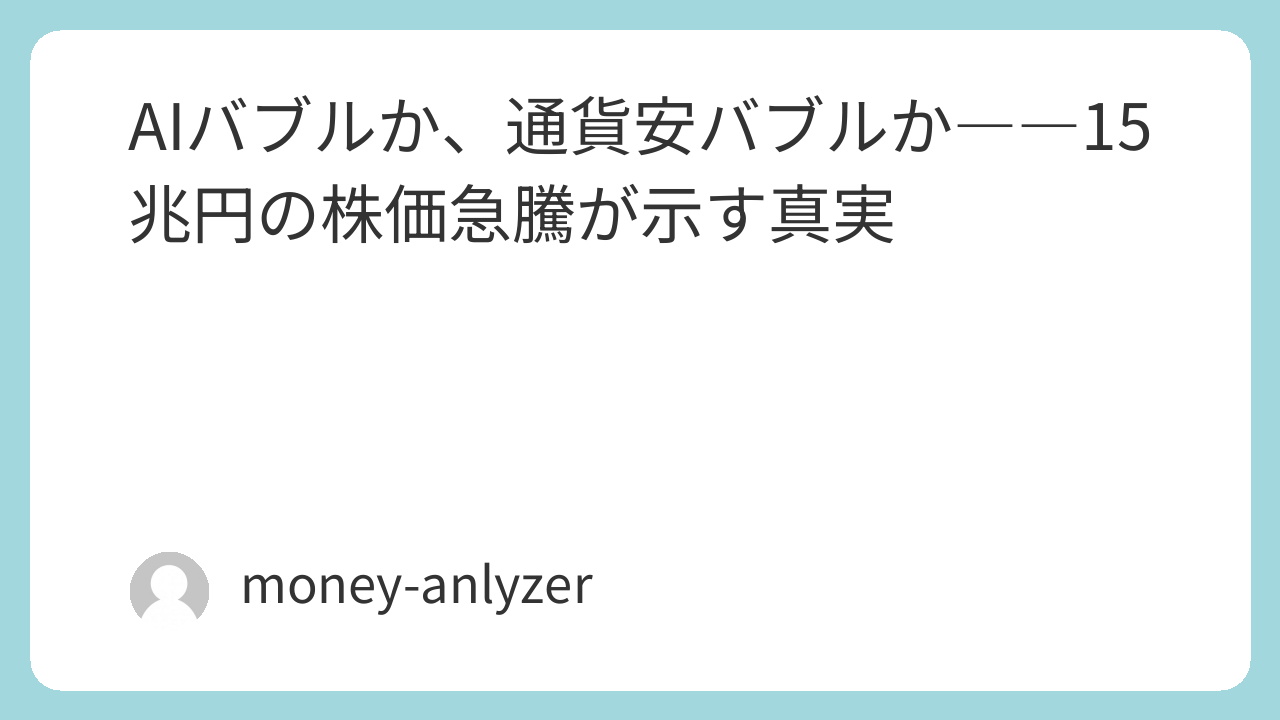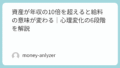2025年10月6日、半導体大手AMDの株価が1日で24%急騰した。時価総額が約1,000億ドル(約15兆円)膨らんだ。
理由はOpenAIとのAIインフラ構築契約の発表だ。
わずか1カ月前の9月には、オラクルが1日で時価総額2,550億ドルという驚異的な増加を記録している。
「これは正常でも健全でもない」
ロバート・W・ベアードのテクノロジー・ストラテジスト、テッド・モートンソン氏はこう警告する。
1987年のブラックマンデーを予測した伝説的投資家ポール・チューダー・ジョーンズ氏も、「現在の環境は1999年よりも爆発的な可能性を秘めている」と述べた。
AIバブルの到来だろうか?
しかし、この問いには重要な視点が欠けている。
それは「通貨の価値下落」という要因だ。
ITバブルとの決定的な違い
多くの専門家がITバブル(1999-2000年)との類似性を指摘する。確かに表面的には似ている。急激な株価上昇、巨額の投資、「今回は違う」という楽観論――。
だが、根本的な違いが3つある。
1. 実需の存在
ITバブル期の企業の多くは、収益モデルが確立していなかった。「将来の成長性」という曖昧な指標で評価されていた。
一方、2025年のAI企業は明確な収益を上げている。エヌビディアは生成AI需要の拡大を背景にGPU販売で過去最高益を記録している。マイクロソフトやGoogleもAIを既存事業と組み合わせ、大きな収益を生み出している。
2. 技術進化の明確性
ITバブル期、インターネットの「使い道」はまだ不明確だった。どのビジネスモデルが成功するか、手探り状態だった。
現在のAIは違う。基礎技術(Transformer、大規模言語モデル)は既に確立されている。進化のロードマップは明確だ:より大きなモデル、より多いデータ、より強力な計算資源。つまり、投資額が性能向上に直結する領域に来ている。
実際、2010年代後半の「過剰投資」と思われたTensorFlow開発やハイエンドGPUへの投資が、2022年のChatGPT登場という革命を生んだ。当時は誰も予想していなかった形で、投資が実を結んだのだ。
3. インフレ環境――見落とされた最重要要因
そして最も重要な違い:インフレ環境だ。
ITバブル期(1990年代後半):
- 低インフレ環境(年率2-3%)
- 紙幣の購買力は安定
- 株価上昇 = 純粋な「期待の過熱」
現在(2020年代):
- 2021-2023年のインフレ率は一時8-9%
- 2025年も完全には収まっていない
- 紙幣の価値が下落している
この違いは、株価上昇の意味を根本的に変える。
「AIバブル」ではなく「通貨安ヘッジ」か
ここで視点を変えてみよう。
エヌビディアの株価は、昨年末を100とすると245.2に達している。S&P500指数の120.8を大きく上回る上昇だ。
しかし、これは本当に「過熱」なのか?
数字で見るインフレの影響
簡単な試算をしてみよう:
【名目ベース】
エヌビディア株価: 100 → 245 (145%上昇)
【インフレ調整後の試算】
2024-2025年の累積インフレ率を仮に15%とすると:
実質株価 = 245 ÷ 1.15 = 213
実質的な上昇率 = 113%
名目145%上昇のうち、約22%はインフレによる目減り分を
埋めているに過ぎない。
これは粗い試算だが、重要な視点を示している。
株価上昇の一部は、単に通貨価値の下落を反映しているだけかもしれない。
資産逃避としてのAI投資
興味深いことに、ポール・チューダー・ジョーンズ氏――AIバブルを警告した同じ人物――は別のインタビューで、インフレ対策としてゴールド、株、ビットコインのポートフォリオを推奨している。
つまり彼は、株高を「成長」としてではなく、インフレヘッジとして見ているのだ。
歴史的に、インフレ期には:
- 現金: 価値が確実に目減り
- 金・コモディティ: 実物資産として価値を保存
- 成長株: 企業の実物資産と将来キャッシュフローで価値を保存
AI銘柄は単なる成長株ではない。最も確実な成長セクターとして、インフレヘッジの役割も果たしている。
インフレ下の「止まれない投資」
この視点は、AI関連銘柄への資金集中の異常なスピードを説明する。
なぜ止まらないのか?
従来の説明:
- AI技術への期待
- 米中の覇権争い
- FOMO(取り残される恐怖)
しかし、より根本的な理由がある:
現金を持つリスクが、投資リスクを上回っている。
ITバブル期、崩壊後に現金に戻れば価値は守られた。低インフレ環境だったからだ。
現在は違う。調整が来ても、インフレが続けば現金の価値は目減りし続ける。「投資しすぎ」のリスクより、「現金で持つ」リスクの方が大きい可能性がある。
だから資金は止まらない。AI銘柄は最も確実な成長セクターであり、同時にインフレヘッジなのだ。
「過剰投資」の二面性
ここでさらに複雑な問題がある。
投資は回収できているのか?
厳しい現実が報告されている:
- 2025年のCDW調査(米国の900人以上のIT意思決定者対象)では、AI投資のROI(投資利益率)を50%以下と見積もる回答者が約3分の2
- 投資額の100%を回収できたと回答した企業はわずか2%未満
- MIT関連の複数の調査でも、AI導入企業の多くが短期的な投資回収に苦戦している傾向が見られる
注: これらは主に2024-2025年の米国企業を対象とした調査であり、調査手法や対象企業の規模によって数値は変動する。またAI技術は急速に発展しているため、今後の回収率は大きく変化する可能性がある。あくまで現時点での傾向として理解すべきデータである。
しかし、これを単純な「失敗」と見なせるだろうか?
歴史は違う答えを示唆する。
2010年代後半のAI投資も、当時は「過剰」と見られていた可能性が高い。
誰もChatGPTのような形での爆発を予想していなかった。
しかし、その投資がなければ、今のAIブームは存在しなかった。
ITバブル期も同じだった。
当事者たちは「本物だ」と確信していた。実際、インターネットのトラフィックは減っていなかった。
株価が崩壊しても、技術は進化し続けた。
そして最終的に、AmazonやGoogleのような巨大企業を生んだ。
過剰投資こそが、次のブレークスルーを生む。
リアルタイムでは、それが「バブル」なのか「必要な投資」なのか、誰にも判断できない。
二重のリスク構造
現在の状況は、二つの異なるサイクルが同時進行している:
技術サイクル: 止まらない競争
過剰投資 → 調整 → 再集中 → さらなる投資 → ...
AIの基礎技術は確立されている。
投資すれば性能は向上する。
一時的な調整があっても、生き残った企業に資金は再集中する。
米中の覇権争いもあり、競争は止まらない。
マクロ経済サイクル: 脆弱な環境
地政学リスク + 債務問題 + インフレ + 政策不確実性
ITバブルの教訓は明確だ。
技術の本質的価値とは無関係に、世界経済・金融環境の変化がバブル崩壊の引き金になる。
そして現在の世界情勢は、ITバブル期(1990年代後半の「平和の配当」期)よりもはるかに不安定だ:
- 米中対立の激化(技術覇権争い)
- ウクライナ戦争、中東情勢の不安定化
- 各国の政府債務が歴史的高水準
- トランプ政権の関税政策など、政策の不確実性
技術的には投資が必要だが、マクロ環境はそれを許容するのか?
このギャップこそが、市場の不安の源泉だろう。
結論:問いの立て方を変える
「AIバブルか?」という問いは、正しくない。
より正確な問いは:
1. 今の株高は何の反映か?
三つの要素が混在している:
- AI技術への期待(本物の需要と収益)
- 過剰投資(次の革新の種を蒔いている)
- 通貨価値の下落(インフレヘッジとしての資産逃避)
この3つは分離できない。
名目株価だけを見て「バブルだ」と判断するのは、インフレという重要な要素を見落としている。
同時に、「単なる通貨安」と片付けるのも、AI技術の革命的可能性を過小評価している。
2. 何が崩壊の引き金になりうるか?
- 技術の限界ではなく、マクロ経済ショック
- 地政学リスクの顕在化
- 金融政策の急転換
- 予期せぬ景気後退
ITバブルもドットコム企業の技術的限界ではなく、FRBの利上げと景気後退が引き金だった。
3. 誰が生き残るか?
調整は来るだろう。
しかし技術進化は止まらない。
ITバブル崩壊後、AmazonとGoogleは生き残り、次の20年を支配した。
次の10年を支配するのは誰か?
投資家への示唆
投資家にとって重要なのは、「崩壊を待つ」ことではない。
選別する視点だ。
現在の株価上昇を「AIバブル」と一括りにするのは、複雑な現実を見落とす。
真実は単純ではない。
そして歴史が示すのは、こうした「過剰」な時代こそが、次の時代を形作るということだ。
1990年代後半の「バブル」が現代のデジタル社会の基盤を作ったように、2020年代の「過剰投資」は、2030年代の技術基盤を作っているのかもしれない。
ただし、その過程で生き残れるのは、ごく一部だけだ。
本記事は2025年10月時点の情報に基づいています。投資判断は自己責任でお願いします。